2.06 洞窟内の生物
煽蝿(コウモリ)
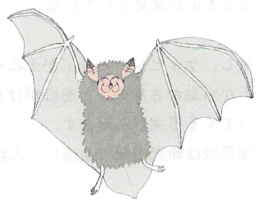
コウモリ(翼手目)は地球上に約950種類が生息している。食果性の大翼手亜目〔オオコウモリ類、約170種〕と、食虫性の小翼手目〔小型コウモリ780種〕に分かれる。日本には、38種類のコウモリが生息していて日本の陸性哺乳類の中で一番、種類が多い。その中で洞窟を好んで棲んでいるコウモリはキクガシラコウモリ、コキクガシラコウモリ、ユビナガコウモリ、テングコウモリなど。
オオコオモリ類は東南アジア、日本〔沖縄南西諸島、小笠原諸島〕、アフリカ、オーストラリアの熱帯、亜熱帯地域に生息している。コウモリは、昔はネズミに翼が生えたものだと思われていた。中国語では「飛鼠」と書き、飛ぶネズミと言われている。世界中でもこれに近い表現で呼ばれてい われている。世界中でもこれに近い表現で呼ばれていることが多い。
しかし、実はモグラの仲間〔食虫目〕の前肢〔手〕が翼に変化し、空を自由に飛べるようになったもので、ネズミの仲間ではない。
コウモリの冬眠と保護について
冬眠中のコウモリの体温は非常に低く、周囲の気温より1~3℃ほど高い程度。これは、冬眠中にエネルギーを消耗しないように、体温を下げて代謝を不活発にする必要があるため。冬眠するコウモリ類は非常に長生きで、大きさが同じくらいのネズミの寿命は2,3年に対してコウモリの場合20年以上生きたものもいる。コウモリたちは、洞外で冬眠するためにたくさん食べてエネルギーを蓄える。コウモリたちが冬眠している洞窟内でコウモリを触ったり、ライトの光や物音などの刺激で起こしてしまうと、コウモリは動いてエネルギーを消費してしまい、冬眠から目が覚める前に餓死してしまうことがある。
冬季に入洞する場合は、コウモリに近づかない、触れない、光をあてない、静かに通り過ぎる、という配慮が大切。ケイビングガイドとして洞窟内の生物の保護も大切なことである。